<共闘 chap.3>
「ブリタニア皇帝は、ある妄想に憑りつかれている。」
唖然としている団員たちにかまわず、ルルーシュは言葉を続けた。
「それは───不老不死。」
議場に集まった黒の騎士団の反応は無かった。
いや、正確には反応できなかったのだ。
それもそうだろう。
真剣な議論をしている最中、「不老不死」などというオカルト用語が出てきたのだ。
「ゼロ……それは一体……」:
扇要が、やっとのことで声を上げた。
「老いた権力者が陥る妄想だ。
何百人といる継承者に皇位を奪われることを恐れ、いつまでも権力の座に留まれるよう、不死となることを望んでいる。」
「はぁっ!? なんだよそれ。
ブリタニア皇帝は、もうろくして頭がおかしくなってるって事か?」
小馬鹿にしたように言い放つ玉城に、ゼロは大きく頷く。
「その通りだ。」
静まり返っていた室内が再びざわつきだした。
「───さっき、遺跡がどうのと言ってたよね。」
朝比奈が、目を細めて問いかける。
ゼロが何故、このような話を持ち出したのか、その真意を確かめるかのように。
「ああ、そうだ。」
そう答えて、ゼロはモニターに数枚の写真を映し出す。
岩山にぽっかりと開いた洞穴。
上部から差し込む日光によって薄明るい内部にそびえ立つ、扉のような岩盤。
その中央には、何かの紋章のような幾何学模様が描かれ、人工物である事が伺い知れる。
「これが、神根島にある遺跡だ。
あの島に漂着した時に、カレンも目撃している。」
団員と共に出席しているカレンが、大きく頷く。
「はい。確かに見ました。
偶然、あの場所にシュナイゼルもいて、何か調査していたようです。」
ざわめきが大きくなる。
「我々が奪ったガウエン。
あれの、ドルイドシステムを利用し、調べようとしていたようだな。」
「その話は以前聞いた。
シュナイゼルは、皇帝の命令で調べていたということか。」
「いや。そうではない。」
扇が、記憶を辿るように呟いた言葉に、ゼロは否定で答えた。
「シュナイゼルは、独自の判断で調査に訪れている。」
その言葉に、主だったメンバーの目が細められた。
「このような遺跡は、世界各地に点在している。」
そう言いながら、ゼロはモニターに世界地図を投影する。
シルエットで浮かび上がる大陸や島々……そのいたるところに小さく点滅する光が現れた。
1つや2つではない。
世界中を網羅するかのように出現した光に、団員たちは目を見張る。
「この点滅は、遺跡の所在地を表しているが、これを見て何か気が付かないだろうか。」
首藤の問いかけに、団員たちは顔を見合わせる。
黙していた藤堂が、呻くように呟いた。
「ブリタニアが宣戦布告し、領土とした国と地域だ……!」
ざわめきが、さらに大きくなった。
「このデータの出所は、シュナイゼルだ。」
帝国宰相の名に、一同が顔を強張らせ、ゼロを注視する。
ルルーシュは、仮面の下で口の端をつり上げた。
「シュナイゼルは、ずいぶん前から皇帝の領土拡張政策に疑問を抱いていた。
領土とした国や地域とは確かに紛争はあったが、政治的な駆け引きによって戦争を回避してきた。
しかし、皇帝の一言で開戦が決まっている。
ここに示した場所、全てで!」
その言葉に、黒の騎士団の誰もがモニターに映る点を刮目する。
ざわめきがさらに大きくなった。
ゼロが切り出した荒唐無稽な話が、にわかに真実味を帯びてきたからだ。
「シャルル・ジ・ブリタニアは、己が欲望のために国民を巻き込み、世界に戦火を振りまき、混乱を作り出した。
我々の敵は、神聖ブリタニア帝国でではない。
ブリタニア皇帝シャルル・ジ・ブリタニアであると、確信した。」
「だから、シュナイゼル達と共闘する?
いくら出資者であるスザクの口添えがあったとはいえ、あの宰相の言葉を信じた根拠は何なんだ。」
相も変わらず、挑みかかるような鋭い目線と声で言い募る朝比奈に、シュナイゼルらとの共闘を納得しかけていた団員達であったが、一気に冷静さを取り戻し、ゼロを見つめる。
鶴の一声とはよく言ったものだ。
ルルーシュは、顔を一瞬引きつらせた。
彼らとの共闘を納得できるよう巧みに誘導してきたものを、あっという間に振り出しに戻されたからだ。
なぜ、シュナイゼルの言葉を信じたのか…か。
ルルーシュは、観念したかのように嘆息を漏らすと、後頭部に手を廻した。
カチリ。
静まり返った室内に、ストッパーが外される軽い音が響く。
黒の騎士団一同は、息を呑んだ。
ゼロが、仮面を外す。
思いもしなかった行動に、視線は釘付けだ。
ゼロが仮面に両手を添え、持ち上げる。
黒い仮面の下から、彼らとは違う色彩の肌が見えた。
続いて、彼らのメインスポンサーである神楽耶と同じ色の毛髪が、サラサラと仮面の中から零れ落ちる。
俯きかけた顔を上げ、彼らを見つめるその瞳の色に、誰もが驚愕した。
その白皙と深い紫の瞳……!
彼ら日本人が、憎み続ける皇帝と瓜二つの特徴を持つ男が、目の前にいる。
「私がシュナイゼルの言葉を信じた理由。
それは……実の兄だからだ。
その言葉に嘘があれば、見抜くことはできる。
彼らの言葉、態度に嘘はなかった。」

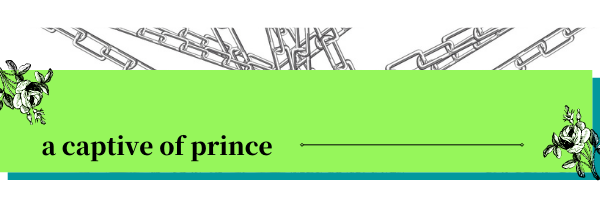
コメントを残す