<共闘 chap.1>
中華連邦西部。赤茶けた砂と岩山ばかりが続く、見渡す限り何もない荒涼とした砂漠を1台のトレーラーが疾駆する。
点在する街と街に物資を運ぶキャラバンのうちの1台のようにも見えるが、この車の前にも後に続く車もない。商用車に偽装されているこのトレーラーは、黒の騎士団のものである。
トレーラー内部は、床に敷かれたラグの上にリビングテーブルと3人掛け用のソファが置かれ、まるで住宅の居間のような設えに改造されている。
そのソファに腰掛けるゼロ、ルルーシュは簡易的に用意された通信機から聞こえてくる音声に頷く。
『各隊、出撃準備完了しました。』
「よし。斑鳩はそのままの高度を保ちながら、目標ポイントで待機。
私の指示を待って、零番隊より順次出撃するように。」
『了解。』
ピッと音を立てて通信が切られる。
その様子を背後で見ていたC.C.とジェレミアが、顔を見合わせ頷く。
「兄さん。僕達も準備に入るね。」
ルルーシュからヘッドホンを受け取り、ロロが確認する。
「ああ。宜しく頼む。」
ルルーシュが引き締まった顔で頷いた。
「しかし……まさか本当にこの共闘が実現するとはな。」
C.C.がクスリと笑いながら呟く。
それに対して、ルルーシュも口の端を上げた。
「全くだ。1年前には想像すらつかなかった。」
だが、これで───
ルルーシュが思い描いた青写真とは大きく変わったが、ナナリーのために創ろうとした「優しい世界」への足掛かりができる。
その事に、ルルーシュの紫紺の瞳が強く煌めいた。
「中華とブリタニアでの同時奇襲。
上手くいくと思うか。」
共犯者の真剣な声の問いかけに、強く頷く。
「勿論だ。そのために俺たちは何度も確認し合った。
こちらは俺が、向こうはシュナイゼルが指揮を執る。
俺には黒の騎士団、シュナイゼルにはスザクという最強の駒がある。
失敗などありえない。」
堂々と言い切るゼロに、緑髪の魔女は満足げな笑みを浮かべる。
「ああ、そうだな。
この日のために、お前は今まで隠してきた素顔を晒したんだ。
そして、信頼を勝ち取ることに成功した。」
「ああ。彼らはもう、ただの手駒ではない。補充も交換もきかない、大切な仲間だ。
結果を出す事だけが信頼を得る条件ではない事を、身をもって知ったよ。」
苦笑する彼に、C.C.はいつもの皮肉気な笑みで答える。
「成長できたじゃないか。坊や。」
「何を偉そうに……
お前こそ、迷いはないだろうな。
以前は同志だったのだろう。あいつらとは……」
気遣しげなその問いに、彼女は肩をすくめる。
「それこそ、いらぬ心配だ。」
「そうだったな。」
2人は顔を見合わせて笑うと、それぞれの持ち場へ向かった。
作戦実行時刻と目標ポイントが刻一刻と近づいてくる。
ルルーシュは、肩の力を抜くように深く息を吐いた。
知らず知らずのうちに身体が強張っていた。
その事に自嘲する。
この、ピリピリとした緊張感には、既視感がある。
どこであったか……
ああ……あの時か───
記憶を手繰り寄せ、ルルーシュは小さく笑った。
ルルーシュが、ロロを連れて深夜の政庁を訪問する数週間前に話は遡る──
東の空に顔を出した太陽の光を浴びながら、黒の騎士団が誇る航空母艦「斑鳩」の甲板に、昨夜この場所から発進して行った輸送機が着陸する。
上空にある雲を茜色に染め上げる日差しに目を細め、扇要をはじめとする黒の騎士団幹部らは、輸送機から降りてくる人物を待った。
ゼロと神楽耶に続いて、身に着けているパイロットスーツと同じ色の髪をなびかせた少女がタラップを降りてくると、その場から安堵の声が上がった。
「カレンっ。」
「扇さん!」
兄とも慕う副指令の姿を確認したカレンが彼の元に駆け寄ると、扇は目じりを下げて彼女の肩に両手を置いた。
「無事でよかった。」
瞳を潤ませて再会を喜ぶ彼らを横目に見ながら、藤堂がゼロと神楽耶の前に進み出る。
「交渉役お疲れさまでした。神楽耶様。」
神楽耶に労いの言葉をかけると、藤堂は厳しい表情をゼロに向ける。
「ブリタニアからの捕虜返還の条件は?」
「うむ。その事なのだが……」
ゼロはそう言って、集まっている面子を見まわす。
「詳細を説明する。全員会議室へ……
藤堂。各部隊の隊長も出席させてくれ。」
彼が了承の意を告げれば、ゼロは満足したように頷き艦内へと歩いていく。
その姿を見送って、玉城はいつになく神妙な顔をした。
「何かとんでもない条件を突き付けられたか?」
空気を読まないタイプの彼でさえわかるほど、ゼロから発せられる気はいつになく緊張していた。
斑鳩内にある大会議室に、ゼロの召集を受けた人物が全員揃うのに、30分はかからなかった。
零番隊隊長の元気な姿に安堵するものの、全員緊張した面持ちで着席する。
巨大モニターを背にした上座の席に、ゼロと彼と共に交渉に臨んだ神楽耶が座る。
「……全員揃ったようだな。」
ゼロの声に、扇と藤堂が頷く。
「ブリタニアは、黒の騎士団エースの返還の条件に、何を提示してきたんだ?」
単刀直入に扇が尋ねる。
穏健派で周囲の状況に合わせるタイプの彼にしては珍しく、まっ先に口火を切った。
それだけ、この交渉が重大であると認識しているのだ。
彼の質問にゼロは鷹揚に頷くと、一呼吸置くと、こちらもきっぱりと答える。
「彼らの要求。それは、我々黒の騎士団との共闘だ。」
「共闘!?」
室内がにわかに騒がしくなる。
「どういう事だ?」
「俺達と一緒に戦う…て意味だよな。」
「何を言ってんのか意味わかんねえよ。」
「ついさっきまで敵同士だったんだぜ。」
ざわざわと、さざ波のように起こる私語を制するように、藤堂が一際太く鋭い声を上げる。
「詳しく話を聞きたい。
ブリタニアは、我々と協力して何と戦うつもりなのか。EUか?そんなことはないだろう。」
世界の覇権を争う三極、ブリタニア、EU、中華連邦……だが、長年に渡る争闘にブリタニア以外の二極は疲弊していた。
中華は幼年である天子の執政として権力をほしいままにしてきた大宦官の横暴の末、クーデターが勃発したばかりで国として機能するまでは時間を要している。
EUはブリタニアによってその勢力圏のほとんどを奪われ、経済によって繋がっていた連合としての機能は崩壊…加盟各国が独自で防衛せざるを得ない状態にまで弱体している。
ブリタニアが脅威するほどの力を持つ国など、実はもうこの世界中にないのだ。
藤堂の問いに、ゼロは頷く。
「勿論、EUではない。いや、戦う相手は国ではない。」
「国じゃない?」
「では、我々のような抵抗組織という事か?」
「勿体つけてねえで、はっきり言ってくれよ!」
たまりかねた玉城が声を上げた。
ただでさえ緊張してこの会議に臨んでいるのである。彼らには、ゼロの言い回しが敵に対して使う話術のように感じられ、苛立ちすら覚える。
「……すまない。言い方が悪かったようだ。
順をって説明しよう。」
ゼロの真摯な対応に、苛立ち始めていた面々も神妙な顔つきで自分達のリーダーを見る。
「まず、私と神楽耶様が交渉した相手だが、オデュッセウス、シュナイゼル、スザクの3人だ。」
「……シュナイゼルをはじめ皇族が3人も?」
藤堂をはじめ扇やディートハルトは、その顔触れに目を見開いて驚く。
たかが捕虜の返還交渉にしては出席者が余りにも高位すぎる。
「彼らは、ブリタニアという国の代表としてではなく、個人として我々と交渉を望んできた。」
「どういう事だ……?」
「彼らが我々との共闘を望む理由……彼らが“敵”としている相手は、シャルル・ジ・ブリタニア。
ブリタニア皇帝だ。」
皇帝の名に、室内は水を打ったように静まり返った。
誰もが声を失い、表情を失った。
ゼロが言わんとしていることに、その場の全員が驚愕していた。
「───それは……つまり……」
喉を詰まらせたかのように、上ずった声で途切れ途切れに扇が声を漏らす。
「そうだ。
彼らは、皇帝に対しクーデターを仕掛ける。
シャルル・ジ・ブリタニアを皇帝の座から引きずり落とすつもりだ。」
淡々と告げる低い声が、広い会議室に響き渡った。
議場は静寂から一転し喧噪と変わった。
「どういう事だよ⁉
シュナイゼルの奴、皇帝を殺して次の皇帝になるつもりなのか。
それを、俺達に手伝えって言うのかよ!?」
「そもそも、こんなことはブリタニアのお家騒動だろ。」
「まったくだ。こっちには何のかかわりもない事だ。」
「ゼロっ。まさか、その条件を呑んだって事か!?」
誰かの声で、視線が一斉にカレンへと集中する。
交渉の詳細はまだ分からない。だが、彼女がここにいるという事が交渉成立の証拠だ。
非難と批判の声がそこかしこから上がる。
「みんな落ち着けっ!」
藤堂が立ち上がり一喝する。
「ゼロ。どうも状況を呑み込めない。
シュナイゼルは何故、そのような“国の恥”ともとれる内容を交渉のテーブルに乗せたんだ?
皇帝の座が欲しければ、シュナイゼルなら我々の手を借りなくとも手に入れられるだろう。」
「ああ。その通りだ。
シュナイゼルは、皇帝をその座から引きずり落とすとは言ってきたが、それは彼らが行う事で、我々にその手伝いをしろと言ったわけではない。
それに───シュナイゼル自身皇帝になる気はないらしい。」
次から次へともたらされる情報に、議場に集まった者たちは困惑を深めていく。
「じゃ……じゃあ。一体誰が新しい皇帝になるって……」
何度も瞬きを繰り返しながら、扇が声を漏らす。
その問いに答えたのは、ゼロではなく傍らに座る少女だった。
「第一皇子、オデュッセウス・ウ・ブリタニア。彼がシャルル更迭後皇帝になります。」
「オデュッセウス…?て……」
誰だぁ?と、玉城が頭を掻きながら首を傾げる。
「天子と結婚するはずだった男だ。」
そのくらい覚えておけと、千葉が眉間にしわを寄せて吐き捨てる。
「………彼を傀儡にするつもりか?」
藤堂が眉を顰める。
彼の懸念はもっともだと、その場にいる誰もが頷く。あの結婚そのものが、ブリタニアの国土拡大を目論むシュナイゼルが仕掛けたものだと認識されているからだ。
「そうではない。帝位が無事オデュッセウスに引き継がれた後、シュナイゼルは政治から身を引き、皇籍も奉還する。
地位も権力も捨てると、そう言った。」
その言葉に誰もが目を剥き息を呑む。
「そんな…あのシュナイゼルが……っ。ありえない!」
ディートハルトが驚愕の声を漏らす。
「ですが、彼は本気です。
表舞台から身を引き、弟であるスザクと静かに余生を送ると……」
神楽耶が、眉尻を下げてそう言う。
室内を、再び沈黙が支配した。
「オデュッセウスは、新皇帝となった暁にはブリタニアという国の在り方を変えると、私たちに宣言しました。」
「───国の在り方を変える……」
扇が呆然と声をもらした。
「そうです。
専制君主制から、議会制民主主義に変えると……政治を国民に還し委ね、身分制度を廃し、いずれは、皇室もなくすと言っていました。」
静かに語る少女の声に、困惑の声がそこかしこから漏れる。
「………そんな事が、できるのか?」
「無理だろう。」
神楽耶から聞かされたことは、現在のブリタニアを根底から覆すという事になる。
あまりにも理想論過ぎて、絵空事のようだ。
不安と、不信を露に私語を交わす彼らに、低く鋭い声が凛と響く。
「できるのか。ではない!
彼らは、それを行うと言っているのだ。」
「だが、ゼロ。オデュッセウスの言う事を実現しようとすれば、ブリタニア国内はとんでもない事になるぞ。
専制君主制から民主制への移行はともかく、身分制度の撤廃というのは……」
既得権益を奪われることになる王侯貴族の反発は、恐らくエリア各地で起きている抵抗運動の比ではないだろう。
藤堂が顔をやや青ざめさせて言うのに、ゼロは静かに頷く。
「ブリタニアが、しばらくの間荒廃するであろうことは誰の目にも明らかだ。
だからこそ、私はオデュッセウスとシュナイゼルに、ブリタニアの超合集国参加を提案した。」
その場の全員が息を呑んだ。
「まさか。」
「……二人は…その提案を受け入れたのか。」
藤堂が、驚愕の表情を隠しもせず問う。
ゼロは大きく頷いた。
誰もが目を見張った。誰もが声を失った。
ゼロ…黒の騎士団が提唱する「超合集国」。それは、そもそも非ブリタニア諸国が、神聖ブリタニア帝国に対抗するために興そうとしている組織である。
そこに、敵対勢力であるブリタニアが加わる……
組織としての意味合いが大きく変貌する。
だが、ブリタニアが参加するには一つ重大な問題がある。
超合集国は、各国の代表による評議会での投票によって物事を決裁する。その投票数の割合は人口比率に比例している。
つまり、大国であるブリタニアが参加するとなると、ブリタニア1国で大量の票が動くこととなり評議会の公正公平さが損なわれてしまうばかりか、ブリタニアの意思が超合集国の意思と同じこととなり、ブリタニアの独裁と変わらない事になってしまうのだ。
「投票権の問題は…どうするんだ。」
扇が眉間にしわを寄せ、呻くように尋ねる。
室内はひりひりとした緊張が支配していた。
ゼロの答えによっては、再び喧騒が襲う事になるだろう。
「その懸念の解消案は、ブリタニア側から提示された。
植民エリアを解放し、国を割ると。」
どっと、どよめきが起きる。
植民エリアの解放。
それこそが、黒の騎士団に集う彼らの目的であり悲願だ。
それが、こんなにもあっさりと、闘争の末ではなく捕虜返還の交渉という極めて平和的な場で、敵側から提示されようとは思いもよらない事だ。
あまりにも急な展開に、この議場に集まったほとんどの人物が呆然とした顔をしている。
そんな中、一人の人物がゆらりと席から立ち上がった。
「あのさぁ……どうにも納得いかないんだけど……」
険しい表情でそう言うのは、藤堂麾下四聖剣の1人、朝比奈省吾だ。
「ゼロも、神楽耶様もどうして、ほんの数時間前まで敵だった奴らが掌返してすり寄ってきているのを、警戒もせず信用している訳?
交渉相手に、あの、シュナイゼルがいたんだろ。
これまで、ブリタニアを動かしてきた張本人じゃないか。」
厳しい口調で、問いかけというよりむしろ叱責に近い言いように、神楽耶の表情が強張る。
傍らのゼロは、大きく息を吐いた。
彼の質問は、想定の範囲だ。いや、むしろ、今までよく誰もこのことを口にしなかったものだと感心する。
「皆だって、本当は一番これが疑問なんじゃないのか⁉」
朝比奈が、煽るように声を上げた。
彼の中には、ゼロに対して拭いきれない不信感がある。
先のブラックリベリオンだ。
攻勢に出ていたにもかかわらず、ゼロが突如戦線離脱したために、ブリタニアの反撃を許し失敗してしまった。
もともと、増援が来るまでに政庁を陥落させるのが目的の短期決戦。それが、指揮系統が崩れたために、ブリタニアに付け入る隙を与えてしまったのが敗因である。
自分が仕掛けた戦争を自ら放棄し、仲間を見殺しにした。
たとえ、捕虜となり公開処刑される寸前だったのを救助してもらった恩があったとしても……いや、違う、恩に感じたことはない。
そもそも、このゼロという男がこの黒の騎士団という組織を興した真の目的を、自分は知らない。他の団員にしても同じだろう。
組織の頭目であるゼロと、彼の元に集まっている者たちの間に乖離があるのは暗黙の了解だ。
ゼロという強烈なカリスマ。これを利用してブリタニア支配から脱却する。
自分達と彼が繋がっているのは、こういった打算でしかない。少なくとも朝比奈はそう思っている。他の者たちも似たようなものだろう。
だからこそ、この報告が余りにも都合よすぎ、気持ち悪いのだ。
不信感を隠しもせず睨みつける朝比奈と対峙するゼロを、誰もが息を呑んで見守るのだった。

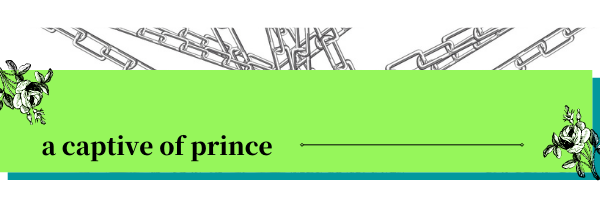
コメントを残す