「お姉さまは、ルルーシュと黒の騎士団が必ず救出してくれます。
私たちは、陛下とその協力者たちを、この皇宮に閉じ込めるのが役割。」
少女の凛とした声が、艦橋に響き渡る。
「ラウンズの出撃もありえるでしょう。
その時は、ギルフォード卿とグランストンナイツに、足止めをお願いします。」
「イエス ユア ハイネス!」
高らかに響く呼応に、皇女は大きく頷く。
「皆さん。どうか、命を大切に。
私は…いいえ、この作戦に参加している皇族全員、シャルル・ジ・
ブリタニアを含めた誰の命も失いたくないと願っています。」
祈るかのように両手を胸の前で組みながら訴えるユーフェミアに、騎士候をはじめとする軍人たちは、静かに首肯するのであった。
「ナイトオブラウンズは、出てくるかな。」
「九分九厘。
ビスマルクが、ナイトオブワンである限り。」
北軍を指揮するシュナイゼルと通信を繋いでいるオデュッセウスは、弟の確信に満ちた答えに嘆息を漏らす。
「そんなに心配そうな顔をしないでください。
スザクならきっと、彼を抑えてくれるはずです。」
「とはいえ、相手はあのビスマルクだよ。」
シュナイゼルの言葉にも、彼の表情から憂いは消えない。
ラウンズとの激突は避けられない。
ならばと、シュナイゼルは、ラウンズが出撃してくる東側をスザクに任せた。
彼が「対ビスマルク」に専念できるように裏工作ずみだ。
ナイトオブナインとナイトオブテンは、反抗勢力の鎮圧という名目で、ユーロに派遣してある。
ジノとアーニャには、残る2名のラウンズ、ドロテアとモニカを抑えてもらう手はずだ。
そして、スザクが駆るナイトメアは、第11世代となる最新鋭機、ランスロット・アルビオン。
セシル・クルーミー女史が開発した「エナジーウイング」は、滑翔だけでなく、それそのものが強力なエネルギー弾にもなる。
ビスマルクのギャラハットに、十分対抗できる機体だ。
「兄上。ここは、スザクとランスロットを信じましょう。
我々がなすべきことは……」
「ああ、分かっているとも。
父上と伯父上の説得は、私たちの役目だ。」
長兄の表情は、常になく引き締まっている。
シュナイゼルも、普段のようなアルカイックな笑みではなく、強い信念を滲ませた表情で応えるのだった。
「ベアトリス。我々が出る。」
ビスマルク・ヴァルトシュタインからの通信に、「鉄女」と誉れ高い特務総監の表情がわずかに曇った。
「しかし、相手は皇子、皇女殿下だ。」
その言葉に、皇帝筆頭騎士は薄く笑う。
「我は、ナイトオブラウンズ。皇帝陛下の剣。
たとえ、皇位継承者であっても、陛下に弓引く存在は排除する。」
当然の事という騎士に、ベアトリスは軽く目を伏せた。
「ああ。そうだな……外は、貴公に任せる。
陛下は、例の間にいらっしゃる。
俗事は、我々で鎮めるのが務め。」
「相分かった。」
血に飢えた獣そのものな獰猛な光を宿した眼を細め、ビスマルクは通信を切った。
「陛下のため戦うことが、お前の本分であったな。
私は、陛下の御心の安寧を保つのが役目。」
そう呟くと、遠い目で、故人となった皇妃をを想う。
マリアンヌ様……
あなたを失ってからの陛下は、何かに憑りつかれたかのように、ご研究に没頭されています。
もう、この現実に…共に生きる私たちには興味がないのかもしれません。
「陛下の御心の安寧を保つか……
あの方はもう、涅槃しか見えなくなってしまっているというのに。」
生きながら、その心はすでに死んでしまっている。
ベアトリスに、主はそのように見える。
このまま、静かに死へと向かっていくのを黙って見守るしかないのを、もどかしいと感じながら、なす術がないと諦めているのも事実だ。
「あの方が、現実に向き合ってくだされば…」
「向き合わせましょう。」
突然かけられた声に、ベアトリスは伏せていた顔を上げる。
ここは特務総監室。
自分一人しかいないはずの空間に、第三者がいることに愕然とした。
何たる失態。
この緊急時に、物思いにふけるとは…!
歯噛みして、声の主を見る。
彼女の座るデスクの正面にある扉が開かれ、第一、第二皇子が並んで立っていた。
その表情には、深い同情と憐憫があった。
「ベアトリス。長く父に仕えてくれているあなたにも、今の陛下の御心は、この世にはないと感じられるのだね。」
眉根を寄せて尋ねるオデュッセウスに、ベアトリスは厳しい表情のまま彼らを見据える。
「皇族専用の地下通路を使って、侵入されたのですか。」
「『侵入』とは、穏やかでないね。
───まあ、この状況では適切か…君には、私たちが父上の首を取りに来たとしか見えないだろうね。」
苦笑を浮かべるシュナイゼルに視線を移すと、元ナイトオブツーは、その任を辞した現在も腰に差している剣の柄に手を伸ばす。
「陛下は常に、あなた様の動向を注視されていました。シュナイゼル殿下。
陛下から、皇帝の座を奪う存在として。」
特務総監の厳しい声に、帝国宰相は肩をすくめる。
「間違っているよ、ベアトリス。
陛下にご退位いただいた後は、オデュッセウス兄上が帝位に就かれる。」
シュナイゼルの言葉に、さしもの鉄女も驚きの表情を浮かべた。
「私たちが事を起こしたのは、陛下のお命が欲しいわけではなんだ。
むしろ、皇位の継承に血で血を洗う惨劇を繰り返す、この国の悪しき習慣は、もう終わりにしなくてはいけない。
父上には申し訳ないが、長年の研究をあきらめ、私たちとともに『今』を生きていただく。
そのための説得に、参上したのだよ。」
「───今を生きていただくための説得…ですか。」
「陛下のいらっしゃる場所へ、案内してくれないだろうか。」
オデュッセウスの懇願に、ベアトリスは一瞬、目を伏せた。
だが、次の瞬間には、先ほどと変わらぬ厳しい顔を向け、挑戦的に口元を吊り上げる。
「私が、あなた方をお連れするとでも?」
「してくれるさ。
あなたも、陛下には現実と向き合っていただきたいのだろう。」
自信満々な声でアルカイックスマイルを向けてくる第二皇子に、特務総監は小さく息をつくと、柄を握りしめていた手を緩めるのだった。

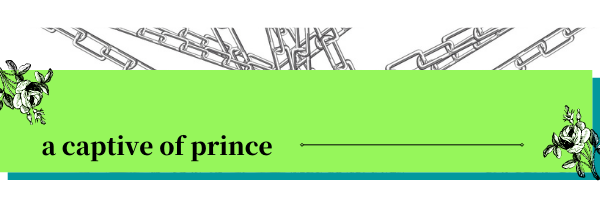
コメントを残す