<共闘 chap.4>
会議室は、再び騒然となった。
それもそうだろう、自分たちのリーダーが敵国の皇子だったのだ。
声を上げる者はまだいい方で、中には顔面蒼白となり、声にならない悲鳴を漏らす者さえいる。
ルルーシュは、自分が与えた衝撃の強さに、一瞬目を見開くと、次には、テーブルの上に置いた両手を固く組み、目を伏せた。
バァーッン!
室内に乾いた音が響き渡る。
「静まりなさいっ!!」
次いで、少女の甲高い声が空気を振るわせた。
恐慌状態に陥っていた男たちの視線が、一点に集中する。
その先にあるのは、仁王立ちで、両の手をテーブルに叩きつけている少女の姿であった。
黒の騎士団最大のスポンサー、皇コンッェルン総裁にして、自称ゼロの妻が再び吠える。
「なんなのです、あなた方は!
ゼロが、日本人でないことは周知の事実。
それが、ブリタニアの皇子であったからといって、このように取り乱してっ。
それでも、日本男児ですかっ!!」
あっけにとられる団員たち。
その中から、プッと声が漏れた。
からからと沈黙を破ったその笑い声も、女性から発せられたものである。
「ほんと、情けないわねえ。
ブリタニアを倒すって言っていながら、ブリタニアの皇子を目の前にして、そんなにうろたえて。」
赤い髪の少女が、からかうように言えば、藤堂の隣に座る女性も呆れた顔で頷く。
渋面の藤堂を挟んで座る朝比奈が、苦笑した。
「まったく、その通りだ──
ブリタニアの皇子が、植民エリアで挙兵するとはな……」
「正確には、“元”皇子だ。
廃嫡されているからな。」
ルルーシュの静かな声に、誰もが息をのむ。
仮面の変声器越しではない、ゼロの生の声。
ただ淡々と事実を伝える、感情のこもらない響きに、目の前の男が抱える闇の重さを感じる。
「藤堂。この方のお顔、見覚えがあるでしょう。」
神楽耶に振られ、藤堂は、改めて自分たちのリーダーの顔を直視する。
見る間に、その表情が驚愕へと変わっていった。
「藤堂?」
再び尋ねかけられ、ひきつった顔で神楽耶を見る。
「神楽耶様…この方は。
ルルーシュ殿下でいらっしゃいますか。」
その問いに、少女は大きく頷く。
藤堂は再びルルーシュに視線を戻すと、すべて納得いったという表情を浮かべた。
「ご無事だったのですね…アッシュフォード家からは、到着前に戦闘に巻き込まれ、お二人とも亡くなられたと……」
その問いかけに、ルルーシュは一瞬驚いたように目を大きくすると、小さく笑う。
「ルーベンめ……抜かりのない奴だ。」
他の者を置き去りにして進められる会話に、一同が唖然とする中、朝比奈だけは、藤堂と同じ顔をしていた。
「そうか。あんた、ブリタニアから留学してきていた皇子か。
枢木の坊ちゃんと一緒に、道場に来ていたな。」
彼の言葉に、千葉もハッとしてルルーシュを見る。
「──そういえば…開戦の前年に、ブリタニアの皇子と皇女が留学生として枢木首相に預けられたと……」
記憶をたどるように扇がつぶやく。
「そうです。この方のお名前はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。
留学という名目で、ブリタニアから人質として枢木首相に預けられました。
ブリタニアは、この方と妹姫様を救出することなく、戦争を仕掛けたのです。」
「──つまり、国に見捨てられた……」
扇が目を見開いてつぶやく。
「ちょっと待ってくれ。
当時君は何歳だったんだ。」
どう見ても10代にしか見えない、仮面の下の素顔に、扇は思わず尋ねかけていた。
「日本に来た時、俺は10歳になったばかりだった。」
重く響くその声に、室内の誰もが目をむき、息を飲んだ。
10歳の子供を人質として差し出し、彼らがいるにもかかわらず、戦いの火ぶたを切ったという非情さにおぞけ立つ。
「ここまでお話すれば、この方がどうして黒の騎士団を興したか、お判りでしょう。」
「復讐か。」
朝比奈の言葉に、ルルーシュは軽く目を伏せる。
「──それもある……だが、俺が望んでいることは、そんなことではない。
……たぶん、君たちと同じだ……」
ルルーシュの言葉に、黒の騎士団は互いの顔を見合わせる。
「俺はただ…妹が笑って穏やかに過ごせる世界を作りたい。
俺の望みは、ただ、それだけだ……」

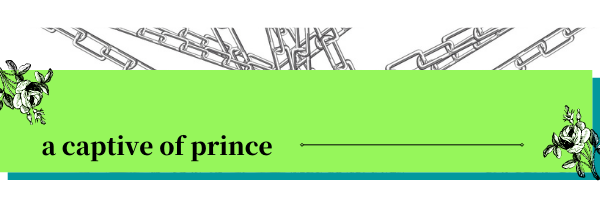
コメントを残す